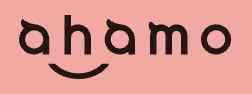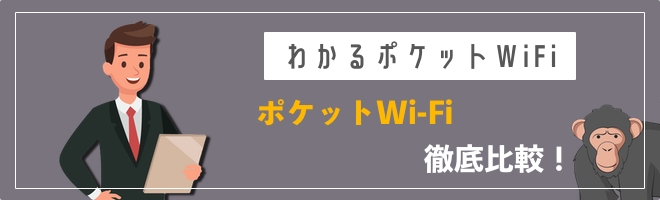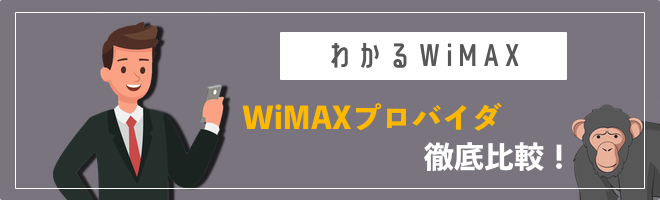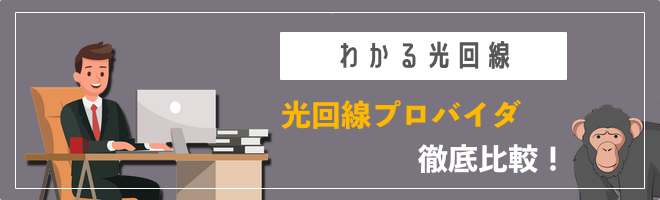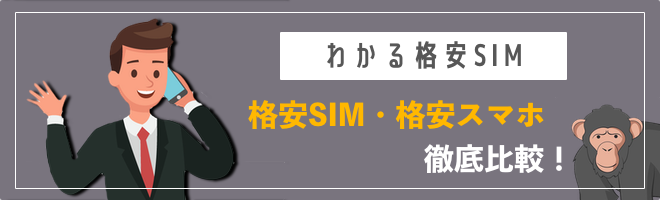子どもにスマホをいつから持たせるべきか悩む人も多いでしょう。この記事ではアンケートを実施し、子どものスマホ事情に関して調査を行いました。
子どもにスマホを持たせるのはいつから?購入時期や対策方法をアンケート調査

子どもにスマホをもたせるのはいつからなのか、ランダムに選んだ258人に対し、以下のアンケートを実施しました。
- 子どもにスマホを持たせたのはいつから?
- その年齢で子どもにスマホを持たせた理由
- 子どものスマホデビュー時に購入したスマホの種類
- 子どもにスマホを持たせる際の不安
- 子どもにスマホを持たせる際に実施した対策
この結果について詳しく解説していきます。
子どもにスマホを持たせたのはいつから?
まず、子どもにスマホを持たせた時期を回答してもらいました。その結果は以下のとおりです。

| 時期 | 割合 |
|---|---|
| 小学生未満 | 3.88% |
| 小学生低学年 | 16.28% |
| 小学生中学年 | 11.24% |
| 小学生高学年 | 15.50% |
| 中学1年 | 29.84% |
| 中学2年 | 4.65% |
| 中学3年 | 6.59% |
| 高校1年 | 9.69% |
| 高校2年 | 0.00% |
| 高校3年 | 0.39% |
| それ以上の年齢 | 0.39% |
| 持たせる予定なし | 1.55% |
本調査では、「小学校低学年」「小学校中学年」「小学校高学年」「中学1年」の時期が大半を占める結果となりました。
子どもにスマホを持たせるタイミングは中学1年生が最も多く約30%で、次いで小学生高学年や低学年に持たせる家庭も一定数あることがわかります。
全体的に、中学進学をきっかけにスマホを持たせる家庭が多い傾向が見られます。
その年齢で子どもにスマホを持たせた理由
次に、その年齢で子どもにスマホを持たせた理由を調査しました。スマホを持たせる時期として多かった以下の年齢ごとに結果をまとめています。
- 小学低学年で子どもにスマホを持たせた理由
- 小学高学年で子どもにスマホを持たせた理由
- 中1で子どもにスマホを持たせた理由
- 高1で子どもにスマホを持たせた理由
順に見ていきましょう。
小学低学年で子どもにスマホを持たせた理由
小学低学年で子どもにスマホを持たせた理由の調査結果は、以下のとおりです。

| 理由 | 割合 |
|---|---|
| いつでも連絡が取れるように | 27.42% |
| 防犯のため | 23.39% |
| 心配だから | 20.97% |
| 習い事や塾など行動範囲が広がったから | 10.48% |
| 周りの子が持ち始めたから | 5.65% |
| 進級・進学したタイミングで | 4.84% |
| スマホを見ている間は静かにしてくれるから | 3.23% |
| 言葉を覚えられる・勉強に活用できるから | 2.42% |
| ITリテラシーを高められるから | 1.61% |
| 電車通学・寮生活を始めるタイミングで | 0.00% |
| 自己管理ができる年齢になったから | 0.00% |
| その他 | 0.00% |
本調査では、「いつでも連絡が取れるように」「防犯のため」「心配だから」といった理由が大半を占める結果となりました。
この結果により、小学低学年だとまだ「自分で身を守る力が十分でない」年齢であるため、「心配だから」「防犯のため」にスマホを持たせる人が多いと分かります。
小学高学年で子どもにスマホを持たせた理由
小学高学年で子どもにスマホを持たせた理由の調査結果は、以下のようになりました。

| 理由 | 割合 |
|---|---|
| いつでも連絡が取れるように | 29.00% |
| 防犯のため | 19.00% |
| 周りの子が持ち始めたから | 16.00% |
| 習い事や塾など行動範囲が広がったから | 15.00% |
| 心配だから | 7.00% |
| 言葉を覚えられる・勉強に活用できるから | 4.00% |
| 進級・進学したタイミングで | 3.00% |
| ITリテラシーを高められるから | 3.00% |
| スマホを見ている間は静かにしてくれるから | 2.00% |
| 自己管理ができる年齢になったから | 1.00% |
| 電車通学・寮生活を始めるタイミングで | 0.00% |
| その他 | 1.00% |
「いつでも連絡が取れるように」「周りの子が持ち始めたから」「習い事や塾など行動範囲が広がったから」といった理由が大半を占める結果となりました。
学年が上がるにつれ広がる行動範囲や交友関係によって、スマホを持たせるようになるケースが多いと考えられます。
中1で子どもにスマホを持たせた理由
中1で子どもにスマホを持たせた理由の調査結果は、以下のとおりです。

| 理由 | 割合 |
|---|---|
| いつでも連絡が取れるように | 21.29% |
| 進級・進学したタイミングで | 14.85% |
| 習い事や塾など行動範囲が広がったから | 14.36% |
| 周りの子が持ち始めたから | 13.37% |
| 防犯のため | 11.88% |
| 心配だから | 8.42% |
| 自己管理ができる年齢になったから | 5.45% |
| 電車通学・寮生活を始めるタイミングで | 3.96% |
| ITリテラシーを高められるから | 3.96% |
| 言葉を覚えられる・勉強に活用できるから | 1.98% |
| その他 | 0.50% |
| スマホを見ている間は静かにしてくれるから | 0.00% |
「いつでも連絡が取れるように」「進級・進学したタイミングで」「習い事や塾など行動範囲が広がったから」「周りの子が持ち始めたから」といった理由が大半を占める結果となりました。
中学生になると、小学生の頃の親の「心配・防犯」といった要素から、子どもの「自立・行動範囲の拡大」による必要性へとスマホ所持の理由が変化していることがわかります。
高1で子どもにスマホを持たせた理由
高1で子どもにスマホを持たせた理由の調査結果は、以下のようになりました。

| 理由 | 割合 |
|---|---|
| 自己管理ができる年齢になったから | 20.34% |
| いつでも連絡が取れるように | 18.64% |
| 進級・進学したタイミングで | 16.95% |
| 習い事や塾など行動範囲が広がったから | 13.56% |
| 防犯のため | 11.86% |
| 心配だから | 5.08% |
| 電車通学・寮生活を始めるタイミングで | 5.08% |
| 周りの子が持ち始めたから | 3.39% |
| ITリテラシーを高められるから | 3.39% |
| その他 | 1.69% |
| スマホを見ている間は静かにしてくれるから | 0.00% |
| 言葉を覚えられる・勉強に活用できるから | 0.00% |
本調査では、「自己管理ができる年齢になったから」「いつでも連絡が取れるように」「進級・進学したタイミングで」といった理由が大半を占める結果となりました。
高校生になり、子どもが自己管理できることを信頼して、スマホを持たせる家庭が多いようです。
子どものスマホデビュー時に購入したスマホの種類
次に、子どものスマホデビュー時に購入したスマホの種類を調査しました。結果は以下のとおりです。
のスマホの種類.png)
| キッズケータイ | キッズケータイ以外の携帯・スマートフォン | |
|---|---|---|
| 小学生未満 | 100% | 0.00% |
| 小学低学年 | 64.29% | 35.71% |
| 小学中学年 | 65.51% | 34.49% |
| 小学高学年 | 30.00% | 70.00% |
| 中学生 | 19.42% | 80.58% |
| 高校生 | 7.69% | 92.31% |
「小学生未満〜小学中学年」の間はキッズケータイを持たせることが多く、小学高学年以降になるとキッズケータイ以外の携帯・スマートフォンの割合が急増しています。
子どもにスマホを持たせる際の不安
子どもにスマホを持たせる際の不安を調査しました。結果は以下のとおりです。

| 不安 | 割合 |
|---|---|
| 携帯・スマホ依存 | 16.43% |
| 不適切なページの閲覧 | 10.87% |
| 勉強への支障 | 9.98% |
| 視力の悪化 | 9.54% |
| ネット上でのいじめ | 9.01% |
| SNS上で知り合った人からの誘い出し | 8.13% |
| 通話料金・通信料金 | 8.04% |
| 有料ゲームやアプリなどでの課金 | 7.86% |
| 睡眠不足・不眠 | 6.98% |
| 情報セキュリティリスク | 6.45% |
| 対面での会話の減少 | 3.00% |
| 扱いが悪く壊しそう | 2.56% |
| その他の不安 | 0.35% |
| 特に不安はなかった | 0.80% |
「携帯・スマホ依存」「不適切なページの閲覧」が大半を占める結果となりました。保護者は子どもがスマホを使いすぎたり、有害な情報に触れたりすることに強い懸念を抱いていることが分かります。
子どもにスマホを持たせる際に実施した対策
子どもにスマホを持たせる際に実施した対策を調査しました。結果は以下のとおりです。
対策.png)
| 対策 | 割合 |
|---|---|
| 使用時間を決める | 23.77% |
| フィルタリングをかける | 19.83% |
| なにかあったら保護者に相談するよう伝える | 15.33% |
| 利用・閲覧できるサイトやアプリを決める | 14.77% |
| 使用場所を決める | 10.27% |
| ペアレンタルコントロールを活用する | 9.56% |
| 壊してもいいように格安機種を選ぶ | 2.95% |
| その他の対策 | 0.70% |
| 特に対策は実施しなかった | 2.81% |
「使用時間を決める」「フィルタリングをかける」が大半を占める結果となりました。保護者はスマホの利用を時間的・内容的に制限することで、依存や有害コンテンツから子どもを守ろうとしていることが分かります。
子どもにスマホを持たせるメリット

子どもにスマホを持たせるメリットは、以下のとおりです。
- 子どもとすぐにコミュニケーションが取れる
- 子どもの現在位置を把握できる・防犯対策になる
- 子ども同士のコミュニケーションが円滑になる
- ITリテラシーを高められる
- 子どもの勉強にも役立つ
詳しく解説します。
メリット①子どもとすぐにコミュニケーションが取れる
子どもにスマホを持たせるメリットの1つ目は、子どもとすぐにコミュニケーションが取れることです。
子どもにスマホを持たせることで、互いの所在確認や急な予定変更、帰宅時間の連絡などがリアルタイムでできます。
今回の小学低学年〜高1で子どもにスマホを持たせた理由のアンケートでは、「いつでも連絡が取れるように」という理由が全ての年代でトップでした。
共働き家庭が増加する現代社会において、スマホは親子間のコミュニケーション機会を確保する強力なツールです。
メリット②子どもの現在位置を把握できる・防犯対策になる
子どもにスマホを持たせるメリットとして、子どもの現在位置を把握できる・防犯対策になることも挙げられます。
最新のスマホには位置情報共有機能が標準搭載されており、子どもの現在地をリアルタイムで確認可能です。
iPhoneでは家族間で位置情報を共有でき、指定場所への到着や出発を通知できます。
Androidのファミリーリンクアプリを使えば、より詳細な位置把握や行動パターンの確認も可能です。
保護者は、仕事中や外出先からでも子どもの移動を見守れるため、不審者対策や災害時の安全確保にも役立ちます。
メリット③子ども同士のコミュニケーションが円滑になる
子どもにスマホを持たせるメリットには、子ども同士のコミュニケーションが円滑になることもあります。
スマホ所有年齢の低年齢化に伴い、クラスメイトや友人間でのグループチャットやメッセージのやり取りが日常化しているからです。
特にLINEなどのメッセージアプリは、宿題の確認や放課後の約束、週末の予定調整など、子どもたちの社会生活に欠かせないツールとなっています。
スマホがあることで、対面では言いづらい内容も気軽に伝えられるため、友人関係の構築や維持にも役立ち、子どもの社会性発達をサポートする一助となるでしょう。
メリット④ITリテラシーを高められる
子どもにスマホを持たせるメリットの4つ目は、ITリテラシーを高められることです。子どものうちからスマホを適切に使うことで、情報機器への理解や操作能力が自然と養われていくでしょう。
小学生のうちから親の指導のもとでスマホを利用すれば、情報の正しい取捨選択やオンラインマナー、セキュリティ意識などを段階的に学べます。
一方、高学年や中学生になってから突然スマホを与えると、使用ルールに反発したり、リスクへの認識が不足したりする可能性もあるでしょう。
幼いうちから親子で話し合いながらスマホを使用することで、将来必要となるIT活用能力の土台を築くことが可能です。
メリット⑤子どもの勉強にも役立つ
子どもにスマホを持たせるメリットとして、子どもの勉強にも役立つことも挙げられます。
例えば、英語の発音学習や自由研究の資料収集、分からない用語の即時検索など、従来の学習方法を補完する強力な学習ツールです。
オンライン個別指導サービスを利用すれば、塾に通う時間や費用を抑えながら質の高い学習機会を得ることも可能です。
子ども用スマホに関しては以下の記事も参考になります。
子ども用スマホをLINEと電話だけにする方法とおすすめ端末&SIM|kodomo no GPS
子どもにスマホを持たせるデメリット

子どもにスマホを持たせるデメリットは、以下のとおりです。
- トラブルに巻き込まれる可能性がある
- 身体に悪影響を及ぼしやすい
- 勉強に支障が出る
- いじめの要因になりやすい
- 有害サイトへアクセスする可能性がある
- 料金がかかる
順に見ていきましょう。
デメリット①トラブルに巻き込まれる可能性がある
子どもにスマホを持たせるデメリットの1つ目は、トラブルに巻き込まれる可能性です。インターネット空間では、保護者の目が届かない場所で様々なトラブルが潜んでいる可能性があります。
- SNSや掲示板での匿名による誹謗中傷やいじめ
- 何気ない写真投稿や位置情報の共有による個人情報の流出
- SNSで知り合った見知らぬ人物からの誘い出し
- アプリでの意図しない課金問題
子どもは判断力が未熟なため、これらのデジタル社会のリスクから自分自身を守る知識や経験が不足しています。
上記のようなトラブルが、子どもの精神的健康に深刻なダメージを与え、犯罪被害に遭う可能性も少なくありません。
デメリット②身体に悪影響を及ぼしやすい
子どもにスマホを持たせるデメリットとして、身体に悪影響を及ぼしやすいことも挙げられます。
今回の子どもにスマホを持たせる際の不安に関してのアンケートでも「視力の悪化」「睡眠不足・不眠」といった健康に関する理由が挙げられていました。
「睡眠不足・不眠」は、就寝前のブルーライト照射が体内時計を狂わせ、成長に欠かせない質の高い睡眠を妨げます。
画面を見る姿勢の悪さからくる肩こりや首の痛みなど、成長期の骨格形成にも悪影響を及ぼす可能性もあるでしょう。
便利なツールであるスマホも、使い方を誤れば子どもの健全な身体発達を阻害する原因となり得るため、適切な使用時間と正しい姿勢の指導が不可欠です。
デメリット③勉強に支障が出る
子どもにスマホを持たせるデメリットには、勉強に支障が出ることもあります。勉強中でも友達からのメッセージが届けば、すぐに確認したくなる心理が働き、集中力が分断されてしまうでしょう。
エンターテイメント性の高いゲームアプリやSNSの存在は、勉強よりも魅力的な選択肢として子どもの意識を奪いがちです。
熱中しやすい年齢の子どもたちは、自制心だけで利用時間をコントロールするのが難しく、気づけば予定していた学習時間が大幅に削られてしまうこともあります。
デメリット④いじめの要因になりやすい
子どもにスマホを持たせるデメリットの4つ目は、いじめの要因になりやすいことです。コミュニケーションアプリやSNSでのグループチャットが、特定の子どもを除外したり、悪口を書き込んだりする「ネットいじめ」の要因になることがあります。
従来の教室内でのいじめと異なり、デジタル空間でのいじめは24時間365日続く可能性があり、逃げ場がありません。
匿名性を利用した心ない発言や、画像の無断拡散など、子どもの精神を深く傷つける行為が容易に行われます。
デメリット⑤有害サイトへアクセスする可能性がある
子どもにスマホを持たせるデメリットとして、有害サイトへアクセスする可能性があることも挙げられます。
例えば、暴力的な映像や性的コンテンツ、反社会的な情報など、子どもの価値観形成に悪影響を及ぼすサイトへのアクセスが容易です。
検索エンジンの検索結果や動画サイトの関連コンテンツから、意図せず有害情報に触れてしまうケースもあります。
ワンクリック詐欺のような巧妙な手口による高額請求の被害やSNS上での悪意ある大人が子どもを狙ってコンタクトを取ろうとするケースなど見えない危険と常に隣り合わせです。
デメリット⑥料金がかかる
子どもにスマホを持たせるデメリットには、料金がかかることも挙げられます。スマホは、初期費用として端末代が3〜8万円程度かかるうえ、毎月の通信料も家族割引を適用しても数千円の固定支出です。
さらに「無料」と表示されるゲームアプリの多くは、ゲーム内購入を促す仕組みを巧みに取り入れており、子どもが熱中するあまり高額課金してしまうケースが後を絶ちません。
動画視聴や音楽ストリーミングなどのサブスクリプションサービスへの加入も、気づかぬうちに家計を圧迫する要因です。
子どもにスマホは持たせるべき?

子どもにスマホは持たせるべきか、以下のメリットとデメリットを参考に検討しましょう。
| 内容 | |
|---|---|
| メリット | ・親子間で迅速なコミュニケーションが可能になる ・位置情報による安全確認ができる ・友人関係が円滑になる ・ITリテラシーが向上する ・学習ツールとして活用できる |
| デメリット | ・ネットトラブルのリスクがある ・視力低下や睡眠障害といった健康への悪影響がある ・学習への集中力低下に繋がる ・いじめの温床になる可能性がある ・有害情報へのアクセスに繋がる ・経済的負担になる |
年齢や成熟度に応じた使用ルールの設定、フィルタリングの活用や親子での定期的な利用状況の確認などの対策を講じた上で持たせるのが現実的でしょう。
子どもにスマホを持たせる際の対策

子どもにスマホを持たせる際の対策は、以下のとおりです。
- フィルタリング機能を利用する
- ペアレンタルコントロールを利用する
- 家族内でのルールを作っておく
詳しく解説します。
フィルタリング機能を利用する
子どもにスマホを持たせる際の対策の1つ目は、フィルタリング機能の利用です。フィルタリング機能により、暴力的コンテンツ、性的表現、詐欺サイトなどの有害情報へのアクセスを効果的にブロックできます。
成長段階にある子どもが不適切な情報に触れる機会を減らし、安心してデジタル世界を探索できる環境を整えることが可能です。
iPhoneではスクリーンタイム設定から、Androidではファミリーリンクを通じてフィルタリングが可能ですが、より包括的な保護を望むなら、各携帯電話会社が提供する専用フィルタリングサービスが最適でしょう。
端末を問わず一括設定でき、年齢に応じたフィルタリングレベルの調整も容易です。
ペアレンタルコントロールを利用する
子どもにスマホを持たせる際の対策として、ペアレンタルコントロールを利用することも挙げられます。
ペアレンタルコントロールにより、子どもの発達段階に合わせたデジタル環境を細かく調整可能です。
具体的には、アプリの利用時間制限、夜間の使用禁止設定、ダウンロード可能なアプリの制限など多角的な管理ができます。
iPhoneではスクリーンタイム機能を通じて、保護者が子どものデバイス使用状況をリモートで把握・制御可能です。
Androidの場合は、ファミリーリンクアプリを導入することで同様の管理が行えます。
家族内でのルールを作っておく
子どもにスマホを持たせる際の対策として、家族内でのルールを作っておきましょう。ルール作りでは、子ども自身も議論に参加させることがポイントです。自分も決定に関わったルールであれば「押し付け」ではなく「約束」として認識し、自発的に守る姿勢が育まれます。
効果的なルールとして「時間と場所の制限」が重要であり、1日の総利用時間を設定し、食事中や就寝前の使用禁止、リビングなど共有スペースでの利用に限定するなどの取り決めが有効です。
「アクセス可能なコンテンツの明確化」として、ダウンロード可能なアプリの種類や訪問可能なサイトを事前に決めておきましょう。
最も大切なのが、困ったことや不安なことがあれば必ず親に相談することを約束し、定期的にスマホの使用状況を家族で振り返る時間を設けることです。
子どもにはスマホとキッズ携帯のどちらを持たせるべき?

子どもにはスマホとキッズ携帯のどちらを持たせるべきか、それぞれ以下のような特徴があります。
| 特徴 | |
|---|---|
| スマホ | ・インターネットの閲覧がしやすい ・豊富なアプリを利用可能 ・高度なコミュニケーションツールが搭載されている |
| キッズ携帯 | ・防犯ブザーなど子どもの安全を守る機能が多い ・インターネットの利用が制限される ・シンプルで使いやすい |
キッズ携帯は、GPS機能による位置確認、緊急時のワンタッチ通話、防犯ブザーなど子どもの安全に特化した機能が充実しています。
インターネット機能が制限されているため、有害サイトへのアクセスリスクが低く、操作も直感的で分かりやすい設計です。
一方、スマホは高度なコミュニケーション機能、豊富なアプリ、インターネット閲覧など多様な用途に対応できる利便性があります。
年齢による使い分けが重要なポイントで、小学校低学年までの子どもにはキッズ携帯の安全性とシンプルさが適しています。
小学校高学年以降は、友人関係でのコミュニケーションツールとしてスマホが主流となっているため、社会適応の観点からスマホの導入を検討するのが現実的でしょう。

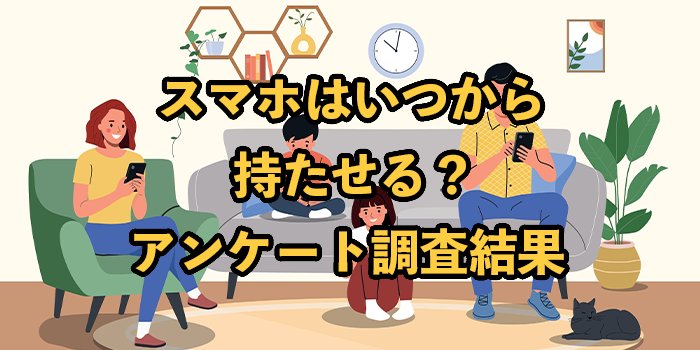





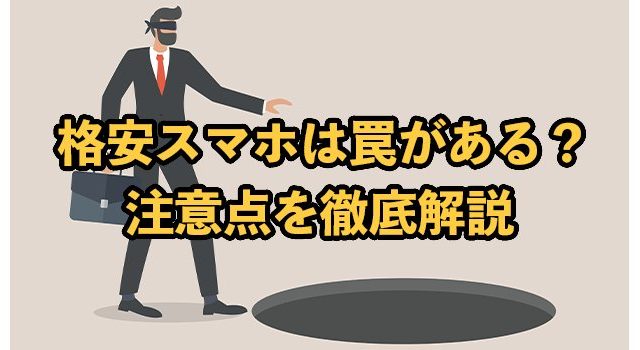
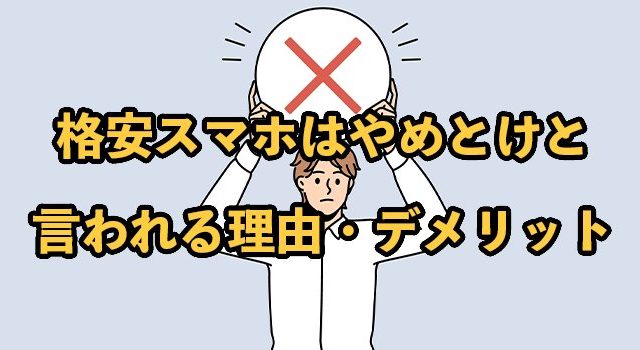


 【27社比較】格安SIMおすすめランキング!2025年に選ぶならどこがいい?
【27社比較】格安SIMおすすめランキング!2025年に選ぶならどこがいい?